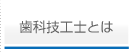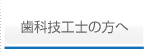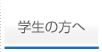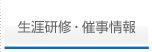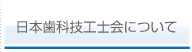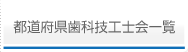『日本歯技』2025年2月号巻頭言
日本歯科技工士会について

「歯科技工士実態調査」の意義
~エビデンスある集団要請を論理的に展開する~
ヒトは誰もが、社会の一員として生きている。私たちの行動や考えは、常に社会とつながり、影響を与えあっている。人間社会の歴史を振り返ると、個人の「殴るな」「奪うな」という社会的な規範から始まり、それがやがて集団としての要請へと発展してきた。例えば「意見を表明する権利」「教育を受ける機会」「適正な労働報酬」などがそれにあたる。これらは社会運動を通じて「生存権の保障」や「営業権の承認」といった具体的な制度となり、近代の市民社会を築いていった。
日本においても、明治時代から「歯科の技工を専門とする者」が存在しているという記録がある。しかし当初は個人の問題に過ぎず、1912年(明治45年)に「歯科技術師設置ノ件」として請願が衆議院に提出されたものの、不採択に終わった。その後、戦後のGHQ統治を経て、歯科技工に関する資格や教育、事業所制度が整理され、1955年(昭和30年)に「歯科技工法」が制定された。これにより、歯科技工士と歯科技工所が法的に認められることとなった。
この制度は、歯科技工士にとって「生存権の保障」や「営業権の承認」という社会運動の成果とも言える。しかし、国は単に歯科技工士のために制度をつくったのではない。厚生省が目指したのは、国民皆保険制度に対応するための歯科医療の安定供給体制の構築であった。つまり、日本の歯科技工は、制度の誕生から今日まで「社会保険」という大きな枠組みの中に組み込まれている。
制度は一度つくられたら終わりではない。時代や社会状況の変化に合わせて見直し、更新されてこそ、真に機能するものである。しかし、制度の改正や更新には、しっかりとした理由が必要である。「困っているから変えてほしい」といった感情論ではなく、論理的で説得力のある根拠が求められる。
そこで日本歯科技工士会は、昭和の終わりから「歯科技工士実態調査」を継続的に重ねる。これは、私たちの現状や課題をデータとして示し、制度改正の根拠を示すための取り組みである。そして2024年(令和6年)、新たな調査データがまとまった。ここでは、私たち歯科技工界が直面する課題が一過性や一時的なものではなく、構造的で積層された問題であることが明らかになっている。
日本歯科技工士会は、こうしたデータを用いて、論理的な集団要請を展開していく。
日本においても、明治時代から「歯科の技工を専門とする者」が存在しているという記録がある。しかし当初は個人の問題に過ぎず、1912年(明治45年)に「歯科技術師設置ノ件」として請願が衆議院に提出されたものの、不採択に終わった。その後、戦後のGHQ統治を経て、歯科技工に関する資格や教育、事業所制度が整理され、1955年(昭和30年)に「歯科技工法」が制定された。これにより、歯科技工士と歯科技工所が法的に認められることとなった。
この制度は、歯科技工士にとって「生存権の保障」や「営業権の承認」という社会運動の成果とも言える。しかし、国は単に歯科技工士のために制度をつくったのではない。厚生省が目指したのは、国民皆保険制度に対応するための歯科医療の安定供給体制の構築であった。つまり、日本の歯科技工は、制度の誕生から今日まで「社会保険」という大きな枠組みの中に組み込まれている。
制度は一度つくられたら終わりではない。時代や社会状況の変化に合わせて見直し、更新されてこそ、真に機能するものである。しかし、制度の改正や更新には、しっかりとした理由が必要である。「困っているから変えてほしい」といった感情論ではなく、論理的で説得力のある根拠が求められる。
そこで日本歯科技工士会は、昭和の終わりから「歯科技工士実態調査」を継続的に重ねる。これは、私たちの現状や課題をデータとして示し、制度改正の根拠を示すための取り組みである。そして2024年(令和6年)、新たな調査データがまとまった。ここでは、私たち歯科技工界が直面する課題が一過性や一時的なものではなく、構造的で積層された問題であることが明らかになっている。
日本歯科技工士会は、こうしたデータを用いて、論理的な集団要請を展開していく。